竹と間伐材で作る「檻」によるイノシシの捕獲方法
竹と間伐材で作る「檻」によるイノシシの捕獲方法
考案者 成瀬 勇夫 氏(岡崎猟友会所属)
岡崎猟友会並びに当研究会のメンバーであり、長年手作りの「檻」によってイノシシの捕獲に努めてこられた成瀬勇夫氏の提案により、お金をかけずに、また環境にもやさしい手作りの檻の作り方と捕獲・管理のポイントをまとめたものを紹介させていただきます。
なお、現在鳥獣捕獲用として竹及び間伐材で作ったものや、鉄製の「捕獲檻」が設置されている場所では、誤って子どもが中に入って閉じ込められたり、仕掛けが外れ、扉が落ちてきてケガをしたりする可能性がありますので、山に入られるかたは、十分注意してください。
捕獲実施者は、被害者又は被害者から依頼された者であって「狩猟免許」を所持する者でなくてはいけません。
捕獲実施者は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」第9条第2項の規定により、有害鳥獣駆除の許可申請(鳥獣捕獲等許可申請)が必要です。
イノシシを捕獲するための心得7か条
1⃣ イノシシを決してあなどらないこと
人が考えている以上に賢く、すぐには捕まらない。
2⃣ 檻を設置する場所を見極めること
設置場所を見誤ると、まったく捕獲できない事がある。
3⃣ イノシシは暗い森を背にして常に警戒しながら行動している
檻全体が周辺の自然になじむように設置すること。
4⃣ 檻を設置したからといって急いで捕獲しようとしてはいけない
まずは檻の周辺にえさをまき、それを食べたのを確認してから徐々に檻の内部までえさをまき慣れさせてから捕獲をすること。
5⃣ 檻での捕獲は2回目以降からが本番である
檻を設置してすぐに捕まったとしても、2回目以降がなかなか捕まらない事が多い。
6⃣ 捕獲できない場所にいつまでも檻を設置しておかないこと
檻を設置しても、一向にイノシシが入る気配がなければ、思い切って場所を移動させる。
7⃣ とにかく檻の管理を怠らないこと
どんなに丈夫で立派な檻でも管理を怠れば捕獲はできない。檻の性能もさることながら、日常の管理(えさやりなど)が大変重要である。
イノシシの生態

- 大変おくびょうな動物である
- 夜行性である
- この頃は人間を恐れないことがある
- イノシシの通路は、一方は見通しが良く、一方は暗い林を背負っている間を好んで通る
イノシシの出る所
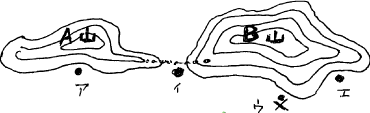
- 大山の近い所
- 山から山へ渡る所
- 初めてイノシシが出た所の餌場
檻を作る場所
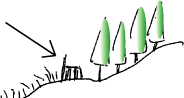
- 管理のやり易い場所
- 土地は乾きの良い場所
- 隠れ易い場所(薮やかや等がある所が良い)
- 少し暗い場所(広くて明るい所は良くない)
- 田畑から離れた場所
檻の作り方
- 自然の素材(孟宗竹・ヒノキの間伐材等)を多く使用して作る(竹は4年以上たったものを使うと良い)
- イノシシが「出られる」と思って出られない檻が良い檻である(太すぎる材料は使わず、幅10から15センチメートル程度がベスト)
- 警戒心を持たれないような檻が良い
- 檻の中の地面は、少し高めにして乾燥するようにする (入り口付近は土をたたいて固くする)
- 入り口の方向は、暗い方に向ける
- 檻の材料に、耐久性を持たせるため防腐剤を塗ってもよい(入り口は逃げやすいため念入りに作ること)
- 檻の場所は、防護柵の近くでもかまわない
- 檻の中には、草や小枝などを入れ自然に近い状態にする
- イノシシ捕獲用檻のイメージ
- 作成方法の資料 ▷▶ 知ってとくとく(農業総合試験場版)の「名人 成瀬さんの竹檻づくり」を参照ください
管理の方法
- イノシシが檻に入るチャンスは、年に3から5回程度ある
- 餌は米ヌカが最適である(残飯でもよいのだが、他の動物が食べてしまうため、米ヌカはイノシシだけが好んで食べ、他の動物は食べない)
日頃食べている物をやり、始めての餌は檻の外で食べさせること - 餌は、檻から30メートルくらい離れた所から餌付けして檻まで誘い寄せる
- 誘い寄せるときは、週に1回は餌をやり、多目にやるとよい
- 10メートルくらい近くに来たら、4メートル間隔に餌をやり、食べたら直ぐにやるとよい(少し多目でよい)
- 1度食べた所は少なくまき、檻の近くは多目にやる
- 檻の近く2メートルぐらいに来たら、檻の中にも餌をやり、いよいよ仕掛けを掛ける
- 仕掛け用の「つる」は、わら・藤つるや木の小枝など自然の物を使い、細い物を使うと良い
- 檻の中の草、木、土などは動かさないこと
- 檻の前の餌を食べたら、入口と檻の中央と2か所にやる
- 檻の中の餌を食べたら、仕掛けの奥まで餌をやる
- ずる賢いイノシシには、檻に2から3度入って、慣れてから仕掛けを掛けるようにする
- イノシシの足跡を確認して、群れが来ていたら仕掛けの位置を奥に移す(仕掛けの前後は針金を檻の外側へ回してつるに付ける)
- 檻の中へ入らない時は、檻の外側に餌をやる
- 3週間以上イノシシが来ない時は、最初に戻って遠くから餌をやり、捕獲後の檻の管理も最初に戻って行うこと
捕獲したあとの檻の管理
- 檻の状態は必ず点検して、不具合は補修し、檻の中の地面中央を少し山盛りし固めること(乾燥するように配慮)
- 小枝や草、落葉などを入れる
- 檻の中に草が繁ったら、餌をやる場所・仕掛けをやるとき歩く場所だけを刈り、中をきれいに刈らない(自然の状態を保つ)
- 檻に付いた血はそのままでよい(特に次の捕獲の障害にはならない)
- 禁猟の時期は檻の修理等をすること
その他
- 檻による捕獲の成功は、檻が4割、管理が6割である
- 檻による捕獲は、猟銃による猟師とのトラブルが少ない
- 自然素材の檻は、自然に戻すことができ環境に優しい
- 間伐材などの利用で製作費が安い(番線などの費用は1万円程度で出来、1つの檻は2人から3人掛りで2日間程度で出来る)
- 集落に小さな檻を数多く作った方が効果は高い(小さな檻の利点は、イノシシにケガが少なく、捕獲しやすく、檻も痛まない)
- イノシシの入りが悪い檻は、早めに場所を変えること
欠点
固定式のものは、設置場所を移動することが出来ない。耐用年数が約3年程である。いずれの檻にしても、要は日々の「管理」がとても重要である。
お願い
昔は今ほどイノシシによる被害はありませんでしたが、近年の被害は甚大であるためやむなく捕獲するのであって、決して動物愛護を軽視するものではありませんのでご理解ください。
















